米問題における小泉農林水産大臣の「随意契約」という発信のおかげで多くの方々がそれぞれの立場で言葉の意味を今一度紐解くことになったのではないでしょうか。行政機関において競争入札に対峙する契約方式であることからマイナスイメージが漂う言葉でしたが、「米をいち早く消費者に届ける」ための手段として奏功したことが、心地よく響く言葉になりました。
転じて民間企業においても取引先の選定おいては、毎日毎日泥臭さが付きまとうのはもう何千年も昔から変わらぬ姿であります。私は人材業界の営業担当として身を置いてきたなかで、他社との競争入札案件には極力距離をおいてきました。結果、指名単独での契約案件が多くを占め批判も数多く浴びながら遂行できてきたことが20年以上営業実績を継続できた所以だと振り返っています。
各企業社会での採用や登用の現場に毎日関わると「人間は平等で、努力は報われ、性別・年齢・国籍・学歴など関わりなく、見た目は大した問題ではない。」などという正論は絵空事であることに直面しながら対応することに何らかの自己哲学が必要になります。現実は人間的センスが高い人材は100社受けると業種や職種など無関係に80社から内定が得られます。しかしながら1名1社にしか身を置けないのでバランスが少し保たれてきますが様々な矛盾との闘いこそ社会生活なのです。
だからこそ人間的価値観が共有できる方々との繋がりは大事にしていきたいと思い邁進しています。


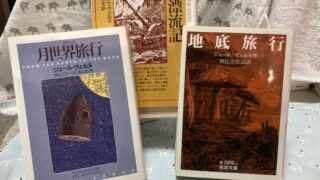
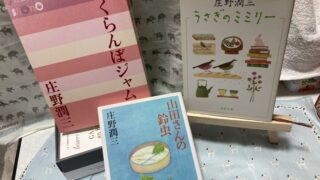



コメント